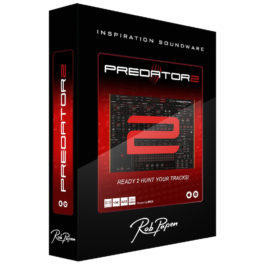RobPapen社最新ソフトシンセ、Predator2の解説を行っている本連載。
初回のプリセット選択から、2回目でOSCのMORPH、3回目でXY PADと強力な新機能を続けて紹介してきました。
今回は少し基本的なところに戻って、改良が加えられたFilterセクションを紹介したいと思います。
進化したFilterセクション
パッと見たイメージはHP FILTERが独立して表示されている以外はPredator1のフィルターとほぼ変わりないですね。

Q(レゾナンス)、Cutoffに続くENV(エンベロープ)、VEL(ベロシティ)、KEY TRK(キートラック)、LFO、MOD WHL(モジュレーションホイール)のそれぞれでカットオフをコントロールする量を調整します。
フィルターエンベロープはRobPapen製品の特徴でもあるADSFRで、ATTACKからDECAYの時間を掛けてSUSTAINのレベルに達したあと、FADEの値に変化し、ノートオフでRELEASEの時間を掛けてフィルターを閉じるという具合です。
エンベロープは自由にアサインして使用できる4つのENVがありますが、これとは別にフィルター専用のエンベロープがあります。
右上のスイッチでカットオフの開閉を逆にできます。
Pre Filter Distortionも健在で、オシレータからの信号がフィルターに受け渡される前にディストーションを掛ける機能ですが、Predator1のSmoothとEdgeに加えてDirtyというメニューが追加されています。
Dirtyはアナログベースのディストーションユニットで、他の2種類と比べてかなりパワフルな印象です。
Predatorはバージョン1の時も2つのフィルターユニットを持っていましたが、以前はフィルター2はQとCutoffのみ操作できました。

F2はフィルタータイプの選択とCutoffとQ/panのノブのみのシンプルな表示です。
Predator2ではFilter 1/2でほぼ同じ機能を持っていて、右上のボタンで表示を切り替えます。

画像はFilter2を表示したところです。
Filter 1/2の違いは、Pre Filter DistortionがFilter1にのみある点で、Predator1と同様にFilter2にのみSplit 1/2があります。
全部で30弱の膨大なフィルタータイプの中で、Splitを選択した場合はFilter 1/2は並列に接続され、Filter2はCutoffとPan AMTのみのシンプルな表示に切り替わります。

Filter2のCutoff以外のパラメータはFilter1と共用し、Pan AMTを上げていくとサウンドにステレオの広がりを与えます。
Split 1/2の違いは、Split2を使用した時のみOSC1がFilter1、OSC2がFilter2、OSC3は両方にアサインされるという点で、Split 1/2のどちらかを使用している間、各OSCのPANのノブは表示されなくなります。
右上の切り替えボタンの1+2を選択すると、Filter 1/2両方を同時に簡易表示します。

この辺りはケースバイケースで使い分けてみてください。
FilterセクションにはもうひとつFILTER LFOがあります。

LFOもENVと同じように、マルチページのENV/LFO/PBページの中に自由にアサイン可能なLFOが4つありますが、フィルター専用のLFOが用意されています。
初めからFilterにアサインされているという点以外は一般的なLFOと似たメニューですが、LFOの適用量をコントロールするAMOUNT CONTROLを操作する項目(画像でMod Whlと表示されている箇所)をクリックすると、モジュレーションホイールやMIDI CCなどの他、XY PADなどもアサインできるようになっています。
また、WAVEFORMではsignやtriangleなどの一般的なウェーブフォームに加えて8つのUser Waveを使用することができます。
User WavesはPredator2ユーザーが自由に描画してウェーブフォームを作成できるという機能で、オシレータのウェーブフォームとしてもLFOのウェーブフォームとしても使用できるという優れものです。
この機能を使用すると、通常の一般的なLFOでは絶対に表現できないLFOが実現します。
USER WAVESについては次回詳しく解説します。
Predator2に興味を持ってくれた方は製品ページからデモバージョンをダウンロード/インストールして試してみてくださいね!
それではまた次回。