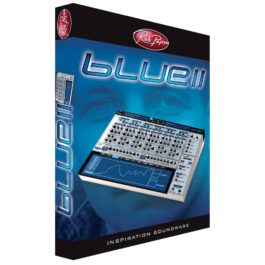こんにちは、Markeing T こと たらまです。「プロが使うRob Papen」の第2弾。今回は作曲家、編曲家、アーティストとして活躍中のとく(toku)、とくPこと、阿部尚徳さんをゲストに迎え、インタビュー形式でお送りします!
Rob Papen「BLUE」と出会ったきっかけ
Marketing T:こんにちは、今日はよろしくお願いします!
とくさん(以下とく):よろしくお願いします!
Marketing T:早速なんですが、Rob Papenのプラグインの使用歴はどのくらいですか?
とく:どのぐらいかなぁ、、4年強ぐらいですね。
Marketing T:4年強ってことは、まだ日本に代理店がないころですね。すごい。
とく:Rob Papenのウェブサイトを見てPREDATORとかも知ってはいたんですが、第一印象が「系統が似てるかな?」というところで、BLUEばかり使ってたんです。ですが、ここ1~2年くらいで他のプラグインにも広がりを感じて使っていますね。
Marketing T:使い始めた順番で言うと?
とく:BLUE、PREDATOR、SubBoomBass、そしてBLADEですね。
Marketing T:リリース順ってことですね(笑)
とく:そうですね(笑)
▶ とくさんが惚れ込んでいるBLUE
Markting T:BLUEと出会うきっかけは何だったんですか?
とく:「フィルターの効きが良くて、透明感があって、プリセットが多くて、さらにアルペジエイターがついているシンセ」を探していて、以前に組んでいたバンドメンバーから教えてもらいましたね。
その当時は、アルペジエイターで細かい設定ができるソフトシンセっていうのがそんなになかったんですけど、その要求に応えられるのがBLUEでした。
Marketing T:なるほど。ということはBLUEに惚れ込んでいるということなので、BLUE推しで話を進めて行きましょう(笑)
▶ BLUEのプリセット
とく:はい(笑)。よくVocaloidを使った曲を動画サイトにアップしてたりもするんですけど、よく使う音が「ピューン!」とか「シュワー!」っていうSE系を好んで使ってます。
Marketing T:SE系の音を作られるときは、プリセットを元にしているんですか?
とく:はい、そうです。
BLUEのバンク19番
Marketing T:それでは、せっかくなので実際に音を出してもらいましょう!

とく:プリセットがすごく充実しているので、いいですよねー。
Marketing T:多すぎてわからなくなるときはあったりします?
とく:さすがに4年以上使っているので、ほとんど覚えています(笑)。アップデートするたびにプリセットも増えて、最近だとダブステップのパッチとかもよくできてますね。
とく:こういった音が手軽に選べて作れるのがいいですね、バンクの19番あたりをよく使いますね。
▶ バンクの19番
Marketing T:お、でました! 皆さん「BLUEのバンク19番」をメモってください(笑)音色以外で、使用感や気に入ってる点とかってありますか?
とく:OSがアップデートするたびに、(OSのアップデートから)1ヶ月くらいで対応アップデートが出てたり。アルペジエイターが「ちょっと変だな」と思ったら、アップデータがいつの間にか出ていたりと、ユーザーフレンドリーなところが好きなところですね。
Marketing T:「対応が早い!」ってことですね。
▶ TABを使って画面が切り替えられる
とく:他のシンセとかは、結構置いてけぼりになっているのもあるので、そういったところもRob Papenのいいところかなと思います。あと、使い勝手がほんとによくて、エンベロープなどの表示、操作もわかりやすいです。ハードウェア(シンセ)を使っていた人にとっては、TABを使って画面が切り替えられるところが、ハードウェア(シンセ)と似た部分があっていいですね。
Marketing T:ページの階層を辿る感覚ですね。
とく:そうです。ローランドとかコルグみたいに懐かしい感じです。
Marketing T:とくさんは、ハードウェアシンセから入られたんですか?
とく:はい、そうです。昔のマルチティンバー全盛期のJXとかXVとかTritonとか。BLUEは、その辺のPCMのデジタルシンセ系を凌駕してる気がします。
実践で使えるBLUE
Marketing T:ちなみに、とくさんが作曲された楽曲で、BLUEが使われている代表的な曲とかって教えてもらっていいですか?
とく:ボカロの曲で『SPiCa』(下記リンク)って曲で使ってますね。ほぼ(全てのパートで)使ってますね(笑)。他の楽曲でもさっきの「19番」あたりを確実に使ってます(笑)
Marketing T:BLUEじゃないと出せない音。なんてあったりしますか? あるいは出しやすい音。
とく:出しやすいところでいうと、6OSC全開のSawLeadなんかは、BLUE独特なエッジ感が出ます。他のトランスっぽい音色系のプラグインにも引けを取りませんし。あと、フィルターのところについている、ディストーションがよく合うというか、よく考えられた作りのディストーションだなというとこが好きだなぁ。

Marketing T:今度、BLUEを使って制作をしてみたいという方に向けて、使い方のコツとか教えてもらったりできますか?
とく:Rob Papenの場合はプリセットが秀逸なので、いじらなくてもいい部分も多いし、いじればいじるほど個性的な変化になるので、自分だけの音を作るにはいいですね。パラメータの変化量も大きいし。
Marketing T:プリセットをいじるときに、どの部分をよく使いますか?
とく:基本的なところですけどエンベロープ、フィルターとそうだな、、、各オシレーターのチューニングも若干いじったりしますね。
Marketing T:わりと細かくいじる感じですか?
とく:はい。ちょっといじるだけで、劇的に変化する音色があったりするので(笑)あとエフェクトがキレイなのと、オーバーサンプリングがいいですね。
▶ オーバーサンプリング
Marketing T:オーバーサンプリングを使う場面とは?
とく:音を際立たせたいときによく使います。最近じゃ全部16xかな(笑)
Marketing T:それでは、最初の話に出ていた「アルペジエイター」に関して質問したいのですが、使う頻度は多いですか?
とく:最終的には自分で打ち込むことが多いんですけど、アイデアを探すときにある音色は「アルペジエイター込み」みたいな音色あるじゃないですか。それがすごくよく考えられているので、制作現場にフィットした音作りになっているなというのを感じます。
Marketing T:ということは、プリセットと一緒にアルペジエイターを奏でて、そのフレーズをモチーフにインスピレーションを受けて、楽曲を制作されるということもあるわけですか?
とく:はい、そうです。BLUEのアルペジエイターはパラメータを細かくいじれるじゃないですか、ボリュームだったりチューニングだったり、フレーズを狙ったうえで、視覚的に作りやすいところが好きですね。
▶ わかりやすいアルペジエイター
Marketing T:確かに、BLUEのアルペジエイター画面はわかりやすいですよね。
とく:みなさん、最終的には打ち込んだほうがよいとは思うんですけど、とっかかりにはいいですね。例えば、1拍目とかをオフにして作るフレーズとかあるんですけど、そういったのも個人的には使いやすいな、と感じてます。KORGのKARMA以降、こういった機能はソフトシンセにはなかったんですよね。
Marketing T:それでは、音のところからは少し話を変えて、今後「このアーティストで使ってみたい」とか「最近この楽曲で使ったよ」ってのはありますか?
とく:最近だと、アンジェラ・アキさんのシングルでアニメ『宇宙兄弟』のED曲『告白』で、BLUEのパッドをVirus Tiと混ぜて使ってます。あ、でもほとんどの楽曲でBLUE使ってます(笑)。これからも使っていきます。
Marketing T:ちなみに、BLUEではさっきのSE系であったり、パッド系だったりと決められたパートで使ったりするのか、あるいはベースのパートなども使ってたりしますか?
とく:シンセサウンドが全面に出すときにも使えるし、バンドアンサンブルの脇役としても使える音色が多いので分け隔てなく使ってますね。
Marketing T:パッド系だとサンプラーの方が音が良いなんてことを言われることも多いのですが、そういった他社シンセと比べてBLUEが良かった点ってありますか?
とく:(動作が)軽い!ってところですね。
Marketing T:それは大事ですね(笑)

とく:他社のプラグインは音色データも膨大なんですけど、結構重いんですよね。BLUEは64bit対応も早かったので、「これしかないな」というので選びました。最初の頃はBLUEを10チャンネル分立ち上げたテンプレートを作って作業開始したりしましたね(笑)
Marketing T:10チャンネルですか!(笑)
専用のハードウェアがほしい
Marketing T:現在お使いのDAWは何ですか?
とく:Logic Proでやってますね。
Marketing T:それでは最後に、Rob Papen製品に求めることはありますか?
とく:専用のハードウェアがほしいですね。フィジコン。例えば、NI MASCHINEでNI MASSIVEのパッチがあるように、Rob Papenプラグイン用のフィジカルコントローラがあるといいですね。
Marketing T:それは制作はもちろんのこと、やはりライブでの使用用途も想定してですよね。
とく:はい、ライブでもBLUEやPREDATORは手弾きで使ってたりするので、パラメータに直接的にアクセスしやすくなればいいな。と、いつも考えてます。ハードウェア(シンセ)から始まっているので、その感覚がありますね。iPadでもいいですけどツマミ感、、、は多分実現しなさそうなので、しいて言えばデザインが地味なのでレベルメータとかが派手になるといいんじゃないかな・・・(笑)BLUE以外のPREDATORやSubBoomBassでもパラメータが一緒の部分があるので、そういった部分をコントロールできる共通パッチなんかもほしいです。フォーラムの方でもユーザーが投稿するパッチが秀逸でよく見てますね。
Marketing T:とくさん作成のパッチを投稿したりとかは?
とく:いや、それは、、(笑)
Marketing T:やっぱり、企業秘密ですか?(笑)
とく:なるべく人に知られたくないけど、だいたいBLUEなので持ってる人にはバレてると思います(笑)
Marketing T:それでは時間になりましたので、本日はありがとうございました!
とく:ありがとうございました。

阿部尚徳
これまでにアンジェラ・アキ、LiSA、アンティック-珈琲店-、植村花菜、Dir en greyなど、多くのメジャーアーティストの作品に参加している作編曲家、アレンジャー、プロデューサー。「へっどほんトーキョー・とくP」として、ボーカロイド代表作は「ARiA」「SPiCa」など。同じVOCALOID楽曲の作家であるハチ・wowaka・古川本舗とともに「estlabo」を結成するほか、ネット系アーティストによるインディーズレーベル「BALLOOM」の総プロデューサーとして、数々のヒット作をチャートに送り出している。2010年、歌い手MARiA(メイリア)とのプロジェクト「GARNiDELiA」を結成、現在活動の主軸になっている。その幅広い音楽知識をバックボーンに様々なシーンでポップセンスを発揮する気鋭な音楽家である。