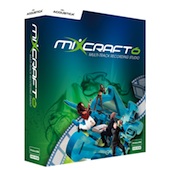(2014/02/28)
楽曲制作を通して、Mixcraftの魅力をお伝えしている本連載。前回予告した通り、今回は空間系エフェクトの「コーラス」についてご説明を行います。
コーラスとは?
コーラスをご説明するために、以下のバイオリン・フレーズを用意しました。
このフレーズは、MixcraftのStrings – Solo : ViolinでMIDIキーボードから打ち込みを行いました。
ではこのフレーズに対し、厚みを持たせたいと思ったとします。
様々方法はありますが、今回は、この音源に対し全く同じフレーズを演奏してみました。
先ほどと比べ、音に厚みが出たと思いませんか?
ここで注意点ですが、コピーをしたわけではなく、もう1度演奏を行っています。
これら2つのバイオリン・フレーズをオーディオに変換し、形を比べてみました。

全く同じフレーズですが、波形の形としては若干ズレがありますね。
これは、実際の演奏でも発生します。
どんなに上手いプレイヤーでも、同じ機材を使って、同じフレーズを演奏しても、全く同じ音(全く同じ波形)にはなりません。
それは、コンマ何秒かのタイミングのズレであったり、微妙な力加減による耳では聞き取れない程の音程の差が発生するためです。
しかし、これは悪いことではありません。
この微妙なズレによって、同じフレーズを同時に演奏すると、独特な音の厚みが生まれます。
これをコーラス効果といいます。
次に実験として、冒頭でご紹介したバイオリン・フレーズをコピーしてみました。

波形はピッタリと一致しますが、実際の音はというと
音に厚みが生まれず、ただ音が大きくなっただけですね。
このように、タイミング、音程に若干のズレがないとコーラス効果は発生しません。そのためコーラス効果を生み出すには、何度も同じフレーズを演奏する必要がありました。
しかし、エフェクトのコーラスを使うことで、コーラス効果を手間無く生成することが出来ます。
では、次にコーラスの原理とパラメータを確認します。
コーラスの原理
コーラスもフランジャーと同様、ディレイを応用したエフェクトです。
ディレイによって、原音から遅れた音を生み出し、そのディレイ音の音程に変化を与え、原音と組み合わせます。これらの働きを図に表すと、以下の通りです。

では、これらのことを踏まえて、コーラスのパラメータを確認しましょう。

- RANGE : ディレイ・タイムを調整します。ディレイ・タイムを短くすると、原音とディレイ音の発音間隔が狭まり、ディレイ・タイムを長くすると、原音とディレイ音の発音間隔が広がります。
- FINE : ディレイ・タイムを、さらに細かく調整します。
- RATE : 音程を揺らすスピードを調整します。値を大きくすると揺れる速度が早くなり、値を小さくすると揺れる速度が弱まります。
- DEPTH : コーラス効果の深さを調整します。
- MIX : 元音とコーラス音の割合を設定します。DIRに回すと原音が、EFFに回すとコーラス音が大きくなります。
- LEVEL : Classic Chorusより出力されるボリュームを調整します。
コーラスの原理、パラメータをご覧いただくと、前回ご紹介したフランジャーと似ていることが分かると思います。
フランジャーとの違いは、コーラスの方がディレイ・タイムを長く設定出来ます。
そのため、設定によってはディレイのように扱うことも可能です。
ここから、ディレイ音の音程に変化を与えることで、音に更なる広がりを追加出来ます。
このようにコーラスは、広がりとともに独特な音色変化も生み出します。
冒頭でもご紹介しましたが、同じフレーズを何度も録音し、音を厚くするテクニックは、かなり以前から行われています。ギターソロやボーカルなどで使用される事が多いテクニックで、それぞれ録音した音が若干ズレることで、音に厚みが加えられます。
また、実際に人が演奏するというアナログ的手法のため、音色に温かさも加えられると言われています。
反対にコーラスを使用した音に関しては、機械的な処理が行われているため、コーラスの設定によっては、冷たい音色と感じるかもしれません。
しかし、コーラスの独特な音色変化は何ものにも代え難い音色なので、要所要所で様々な手法を使い分け、理想の音色を追い求めてください。
次回は空間系エフェクトとしては最後となる、フェイザーをご紹介します。
それでは!
- 前回記事:フランジャー編
- 次回記事:フェイザー基礎編
投稿者:うえだ

カスタマーサポート担当。
丁寧かつ迅速なサポートを心がけています。
弊社取り扱い製品についてお困りの際はお気軽にご連絡ください。